気をつけていても髪が広がる!髪質によるボリュームを抑えるためのブローテクニック
湿気の有無を問わずいつも髪が広がりやすい、ボリュームを抑えるシャンプーを使っているはずなのにハチ部分が膨張して頭が大きく見えてしまう……とお悩みになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
元々髪の1本1本が太くハリやコシが強い髪質ですと、ボリュームダウンするシャンプーやスタイリング剤を使っただけでは髪の広がりを防ぐことが難しいです。
なのでこれらと合わせてブロー方法にも工夫を取り入れてみてください。
あそこで今回は、髪質によるボリュームを抑えるためのブローテクニックについて紹介します。
スタイリングにはボリュームを抑えるオイルを活用して

髪が太くハリ・コシが強い方は、水分が多く含まれるミストタイプやミルクタイプのスタイリングだとボリュームが抑えきれないことが多いです。
反対にオイルであれば塗布した部分に重みが加わり、重力で下に引っ張られるため効果的に髪をまとめることができるようになります。
質感は重く、それでいてベタつかないヘアオイルを手のひら全体に薄く伸ばし、膨らみやすいハチ下から毛先へ向かう髪の内側部分に塗布して軽く馴染ませます。
毛先が傷んでいたりもっとまとまりがほしい方は、その後毛先にもオイルを馴染ませてくださいね。
膨らみやすいハチ下は下に引っ張って乾かす

オイルを塗布し終わったら髪全体を軽く濡らしてブローをしていきます。
7割程度乾いたところで、トップの髪をピンで留めてハチ下が見えるようにブロッキングします。
その後ハチ下の毛束を人差し指と中指で挟みながら、下方向に髪が真っ直ぐになるまで引っ張りつつブローしましょう。
こうすることで膨らんで頭が大きく見える原因となるハチ下のボリュームが減り、髪質や湿気の影響を抑えてコンパクトに髪がまとまるようになります。
また顔周りの髪のボリュームが気になる方は、ハチ下と同様に下方向に引っ張りつつブローしてくださいね。
髪表面部分とトップは持ち上げて空気を含ませる

ハチ下のブローが終わったら、ピンを外して髪表面とトップをブローしましょう。
ボリュームを潰したくない部分は髪を持ち上げ、髪と地肌を傷めない距離から根本に風を当てていきます。
上記のブローテクニックと組み合わせることによって、髪の奥側のボリュームを抑えながらもぺったんこになりすぎない、髪表面がふんわりとした仕上がりになりますよ。
マスクを着用する期間が長引いて以前よりも肌が荒れやすくなった、凄く荒れているわけではないけど常に何かしらの不調が見られる……とお悩みになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
マスクを着けるとその内部は常に高温多湿で蒸れた状態になるので、肌が過敏に反応し炎症を起こしてしまいやすくなります。
そこで今回は、鎮静スキンケアが必要な肌に見られるトラブルサインについて紹介します。
普段使っている化粧水や美容液がヒリヒリするようになった

免疫力が低下し肌が敏感になっていると、ちょっとした刺激でも炎症を起こしやすくなります。
肌を見ても赤みやくすみなどトラブルが起きているようには見えず、それでも使い慣れている化粧水や美容液が突然ヒリヒリするようになった時は肌が炎症を起こす寸前の状態と言えます。
マスクをコットンや絹など肌触りが柔らかい素材のものに変更する、肌の状態が元に戻るまで敏感肌用の低刺激タイプのスキンケアアイテムを使用するなどの対策を取ってみてください。
そしてコスメもなるべく低刺激のオーガニックタイプを使うとトラブルを抑えやすくなります。
ニキビほど盛り上がりのない赤みが顔のあちこちに見られる

赤ニキビのようにぶつぶつ盛り上がっていたり痛みがあるわけではないけど、頬や小鼻などの肌表面が部分的に赤くなることもありますよね。
盛り上がりのない赤みは肌表面に近い部分で炎症が起きている証拠です。
マスク着用時や洗顔・クレンジング時の摩擦によって肌が傷んでしまっているため、赤みが見られたらその部位は極力擦らないようにして肌が沈静化するのを待ちましょう。
肌がくすんで透明感が失われている

肌色がくすんでなんとなく冴えなかったり暗く見えている時は、乾燥とメラニンの過剰分泌が考えられます。
肌の奥が炎症を起こすと逃げる水分を内側に留めようと、体はメラニンを盛んに分泌するようになります。
美白ケアをしていてもくすみが取れない時は、低刺激かつ浸透力の高いスキンケアアイテムを使って肌の内部を徹底的に潤しましょう。
炎症が治まればメラニンの生成量も通常通りに戻り、毎日のターンオーバーによって次第にくすみも晴れていきますよ。
ターンオーバーを促進するためには食事内容を見直して毎食タンパク質を摂り、毎日安定した睡眠時間を確保するといいですね。
椿油が髪にいいと聞いて使ってみたけどベタベタしてすぐに使用を止めてしまった、椿油は健康的な髪に使うには質感が重すぎる……とお悩みになったことがある女性も多いかと思います。
伝統的な椿油は昔から髪のケアに使用されてきましたが、濃密なテクスチャなのでそのまま使ってしまうとひどく髪がベタベタしてしまう扱いづらさがありますね。
そこで今回は、少し扱いづらい椿油の簡単活用術3選について紹介します。
シャンプー前のオイルパックでツヤツヤサラサラに

頭皮と髪全体が酷く乾燥してパサついている時は、シャンプー前のオイルパックがオススメです。
椿油を適量手のひら全体に伸ばし、シャンプー前の乾いた状態の髪に満遍なく塗布していきます。
全体的にしっとりしてきたらすぐにお湯で流し、その後で普段通りシャンプーとコンディショナーをしてください。
1回のシャンプーでは重い椿油は落とせきれませんが、再びシャンプーをすることで普段よりもツルツル感のある髪に仕上がるようになります。
1回行えば保湿感が数日持続するので、週に1,2回スペシャルケアのつもりでやってみてください。
コンディショナーに数滴混ぜて保湿力アップ

髪に特にトラブルはないがツヤとまとまりがほしい、という時はコンディショナーに椿油を数滴混ぜる方法がオススメです。
ロングヘアには4,5滴、ミディアムヘアには3滴前後を目安に椿油を加え、いつもと同じようにシャンプー後コンディショナーを塗布してください。
その後5分ほど放置し洗い流すと、椿油のベタベタ感は全くなくそれでいてまとまりのある髪に改善されますよ。
この方法は頭皮の皮脂量が多い方や髪の毛に毛束感が出やすい方でもベタつかないので、デイリーケアとして手軽に取り入れられます。
コンディショナー後の椿油水で髪をコーティング

髪をしっとりさせたいけどアウトバストリートメントとして使うには重すぎた、という方は椿油水を作って髪にさっと馴染ませる方法をオススメします。
作り方は簡単で洗面器に半分程度お湯を張り、そこに椿油を2,3滴垂らしてよくかき混ぜます。
それをシャンプーとコンディショナーを済ませた髪に流すようにしてかけるだけです。
椿油を原液で使うよりも質感が軽くなりますし、髪を満遍なく保湿することができます。
椿油水をかけた後はいつも通りドライヤーを当てて、生乾きにならないようにしっかり乾かしてくださいね。
梅雨から夏にかけての時期は頭皮にブツブツができやすい、ちゃんとしっかり洗っているはずなのにニオイやベタつきに悩む時がある……とお困りになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
梅雨から夏の時期は湿度も非常に高くなりますし、気温の上昇に伴って頭皮が蒸れやすくなりニキビやニオイ、肌荒れなどのトラブルに陥りやすいと言われています。
そこで今回は、健康的な頭皮を維持する方法3選について紹介します。
肌当たりの優しいアミノ酸系シャンプーを使う

梅雨時になると肌が荒れたりブツブツとした頭皮ニキビができる、敏感でフケが出やすいといった時はアミノ酸系シャンプーを活用してみてください。
アミノ酸系シャンプーは洗浄力はさほど強くありませんが、それ故に頭皮に刺激を与えずに髪を洗えるようになります。
刺激がないので荒れた頭皮に使ってもしみることがなく、継続的に使用することで少しずつ頭皮状態を健康にしていくことができます。
シャンプーをする時は予めお湯で頭皮と髪の根元をよく洗い流しておくことで、更に汚れ落ちがよくなります。
まめに頭皮マッサージやヘッドスパを行う

髪の毛も肌の一部なので、血行が良くなると再生力が高まったり発毛が促進されたりします。
頭皮の血行が悪くなると頭皮が荒れた時に治るまでに時間がかかる他、抜け毛量が多くなり薄毛に繋がるリスクが高まります。
シャンプーをする時に指の腹に力を入れて頭皮全体を揉んだり、柔らかいシリコンブラシを使ってマッサージしつつ毛穴を洗浄すればニオイやフケ、ベタつきなどのトラブルもケアすることができますよ。
そして頭皮の汚れや毛穴詰まりを除去できるヘッドスパも頭皮トラブル改善には役立つので、時間があればやってみることをオススメします。
頭皮荒れが気になる時はカラーリングやパーマを控える

美容院・セルフを問わずカラーリングやパーマは頭皮に大きなダメージを与えます。
薬剤は刺激が強く、定期的に繰り返し使われることで頭皮に刺激が加わり傷みに繋がってしまいます。
カラーリングやパーマをするとがらりと雰囲気は変わりますが、髪や頭皮環境のことを考えると頻繁に行うことは望ましくありません。
特に既に弱っている頭皮や梅雨時・夏など頭皮が敏感になっている時期はトラブルが起きやすくなったり悪化する恐れがあるので、そうした時は控えた方がいいでしょう。
野菜が苦手でサラダや野菜系のおかずを食べる気にならない、食物繊維が足りず便秘がちなので食事を見直したい……とお悩みになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
野菜は体には良いのですが美味しく食べるには凝った調理が必要だったり、味にクセがあったりするので「凄く好き!」という方以外は不足しがちかと思います。
そこで今回は、体を温め内側からキレイを作る簡単野菜スープレシピについて紹介します。
どこでも手に入る食材で作りやすい

ダイエット食や美容食というと高価だったり珍しい食材を使うレシピも多いですが、野菜スープは非常に簡単かつどこでも手に入る食材で作ることができます。
そしてレシピのアレンジ性も高く、作る度に具材を変えれば飽きにくくなるので長期的に取り入れられるのも魅力です。
小鍋いっぱい分の基本的なレシピは以下の通りです。
・コンソメキューブ3個程度
・キャベツ 5枚程
・人参 1本
・玉ねぎ 1/2個
・トマト 1個
・塩コショウ お好みで
小鍋いっぱいにお湯を入れたら沸騰させ、一口程度に切った野菜を入れて柔らかくなるまで煮込みます。
野菜の固さが気になったり時短したい方は、予め野菜をレンジで温めてから煮るといいでしょう。
その後コンソメ粒と塩胡椒など調味料を入れてお好みの味に整えて完成です。
抗酸化作用が高いトマトで毎日アンチエイジング

トマトに多く含まれているリコピンにはビタミンEの100倍もの抗酸化作用があると言われています。
老化の元となる活性酸素を除去し、継続的に食べることによって肌のアンチエイジングをサポートします。
そして血糖値の急上昇を防ぐ効果もあり、食事の最初に食べることで血糖値の上昇が緩やかになり太りにくい体に整えます。
煮込むことで野菜もたっぷり食べられる

1日に必要な野菜をサラダで食べようとすると、あまりにも量が多く忙しい方や野菜好きでない方にとってはキツイですよね。
野菜は煮込むとかさが減って食べやすくなるので、このスープを日々の野菜不足の解消に役立ててください。
レシピで挙げた野菜はどれも食物繊維やビタミンが豊富ですから、便秘や便秘からくる肌荒れ、ビタミン不足による肌のハリ・ツヤを改善できますよ。
これ以外の野菜を入れても美味しく仕上がるので、例えばもっとかさ増しをしたい時は低カロリーなきのこ類を加えたり脂肪燃焼効果をアップさせたいならトマトを追加したりとその時の体調によって色々試してみてください。
夏場は汗も多くてオイルを塗ると凄くテカる、乾燥対策をしたいけど肌が厚ぼったく重くなるアイテムが苦手……とお悩みになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
乾燥対策や小じわ対策としてスキンケアの締めに美容オイルを使っている方は多いですが、使用感の重さが気になる方はオイルよりも乳液を締めに使う方が向いています。
そこで今回は、しっとり肌の保湿対策の締めに乳液をオススメする理由について紹介します。
美容オイルほど重くなく皮膜感が少ない

スキンケアの締めに何のアイテムを使うかというのは人によって大きく分かれるポイントです。
テクスチャの重さで言えばオイル、クリーム、乳液の順でしっかりとした保湿感が得られ、塗った時の質感も重くはっきりとした皮膜感があります。
乳液はこれらのアイテムの中でも水分・油分のバランスが半分半分で、塗った後の肌はしっとりしながらもベタつかないのが大きな特徴です。
皮膜感もないので塗った後の肌の厚ぼったさや、オイルやクリームでは保湿過剰が気になる方に向いています。
するすると伸び肌馴染みが良い

乳液はオイルやクリームと比較すると水っぽさのある液状なので、少量でも顔全体にスムーズに伸ばすことができます。
少量でもよく伸び肌を保湿できるということは肌のベタつきを防止することに繋がるため、普通肌や油性肌、混合肌などの皮脂量が多い肌と相性が良いです。
更に柔らかいテクスチャをしていることもあって、塗ってすぐに肌に馴染む点も魅力です。
クリームやオイルなどこってりした油分量が多いアイテムですと馴染みきらずベースメイクが崩れやすくなるのですが、乳液ならばすぐに浸透して肌表面には薄く残る程度なのでベタベタ感を気にせず過ごせるようになります。
スキンケアアイテムを何層も塗り重ねなくて良い

皮脂量が元々多いと時間経過によるメイク崩れが起きやすい肌質です。
そうした方はスキンケアアイテムやベースメイクを何層も塗り重ねることで、皮脂が混ざりヨレやすくなるのです。
スキンケアの締めにマルチタイプの乳液を使えば、肌の保湿と水分の蒸発を防ぐパック効果、化粧下地効果などが1本で得られます。
すると今までよりも重ねるアイテムの数が減るので、多少皮脂が分泌されてもベースメイクが崩れなくなったりメイク直しが簡単になったりするメリットがありますよ。
夏の乾燥をケアするためにオイルを使いたいけどベタついたら困る、日中はさらっと仕上げ夜はしっかり保湿をしたい……とお考えになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
美容オイルは肌の水分を逃さないように蓋をする効果を持ち保湿に役立ちますが、油ですのでベタつきそうだったりニキビが悪化しそうといったイメージもあるかもしれません。
そこで今回は、不慣れでも使いやすいオススメ美容オイル3選について紹介します。
さらっと軽く肌なじみが良いオリーブスクワランオイル

普通肌・油性肌・混合肌の方に向いているのはオリーブスクワランオイルです。
美容オイルの中でも最も軽い質感をしていて、肌表面をしっとりと保湿しますがしばらく時間が経つとサラサラとした手触りに変わるのが特徴です。
使うことで肌に柔らかさが出るので、肌の乾燥をケアするだけでなく軽度の表情小じわを埋めてカバーできる嬉しい効果もあります。
またスキンケアの最後に塗ることで肌にツヤを仕込むこともできるので、適度にツヤ肌になるセミマットメイクをしたい方にもうってつけです。
肌の水分・油分バランスを整えるホホバオイル

オリーブスクワランオイルよりももう少ししっかり保湿をしたい方にはホホバオイルも非常に使いやすいですよ。
テクスチャはサラサラとしていてベタつきませんが、よりしっとりと肌に密着して肌内部の水分を留めてくれます。
保湿過剰になりたくない時は1,2滴、就寝前など集中的に保湿ケアしたい時は3,4滴といった具合にどんなシーンでも活躍するオイルです。
紫外線をたっぷり浴びてしまう方にはローズヒップオイル

夏は紫外線を浴びることによるエイジングサインの現れが非常に気になりますよね。
紫外線をたっぷり浴びてしまった時や日頃からエイジングケアをしたい方、乾燥肌の方にはローズヒップオイルがオススメです。
ローズヒップオイルは非常に多くのビタミンCを含んでおり、紫外線による肌荒れやシミなどを予防する働きがあります。
こちらは上に挙げた2つのオイルよりも重くとてもしっとりしたテクスチャですので、就寝前の使用に向いています。
油性肌だけど紫外線ケアをしたい方は、朝はオリーブスクワランオイル、夜のお風呂上がりにはローズヒップオイルといった具合で使い分けるといいでしょう。
可愛いアイシャドウパレットを見つけたけど全色ラメぎっしりで使い道がわからない、見た目に惹かれてラメオンリーのアイシャドウパレットを買ったけどギラギラして使いこなせない! とお悩みになったことがある女性もいるのではないでしょうか。
敷き詰められたキラキラとした眩しい輝きが女性の心をくすぐるラメオンリーパレットですが、普段使いすると派手すぎるのでは? と挑戦しづらいアイテムでもありますよね。
そこで今回は、キラキラ感が魅力のラメオンリーパレットを初心者でも使いこなす3つのコツについて紹介します。
高発色ラメシャドウを単体グラデーション塗り

1つのパレットに何色もラメアイシャドウが配置されたものですと、キラキラしたラメを主体とした無色に近いタイプとラメがたっぷり配合されつつ高発色なものの2通りが入っていることでしょう。
無色に近いラメシャドウはベースカラーやニュアンス変化には使えますが、発色が弱く単体塗りは適しません。
一方でラメがぎっしり入っていて発色も良いタイプですと、単色塗りでもしっかり目元を彩ることができます。
華やかかつヌケ感のあるメイクをしたい時は、このタイプのアイシャドウを普段アイシャドウを塗っている時と同様にグラデ塗りするといいでしょう。
いつも使っているアイシャドウに重ねて輝きをプラス

あまり冒険はしたくないけど今のメイクはマンネリ化している、と思った時はラメパレットの出番です。
いつものアイシャドウを使った後、その上にラメシャドウを重ねればメイク系統はそのままに華やかな輝きを加えることができます。
もしくは高発色タイプのラメシャドウを薄く瞼全体に塗り重ねることで、ニュアンス変化も楽しめますよ。
涙袋や目尻、瞼中央にさりげなく単体使い

メイクをしていて「もう少しだけ華やかにしたい」と思う時はよくありますが、そんな時にもラメパレットは活躍します。
目元を明るく見せたり涙袋を作りたい時は、白やクリーム、ピンク系のラメシャドウを涙袋部分に塗ると簡単に立体感が出せます。
またゴージャスや色気のある印象に見せたい時は高発色ラメシャドウを目尻に使ったり、黒目を潤んだように見せたい時は瞼の上下に無色に近いラメシャドウを塗るといった使い方もできます。
「今のメイクでは少し物足りない……」というお悩みを解決してくれるパレットなので、1つ持っておくとメイクの幅が広がります。
ダイエットが長期化するといつも肌や髪がボロボロになる、ダイエットをしている期間は体力が落ちたり冷えを明らかに感じるようになる……とお悩みになったことがある女性も多いのではないでしょうか。
ダイエット食と言うと糖質は摂らない、脂っこいものはNGなどと刷り込まれがちですが極端な食生活の変化はデメリットの方が多いのです。
そこで今回は、太らないために意識したい、今日から実践できる健康的な食事の3つのコツについて紹介します。
毎日1食でもいいので米を食べる

一時期話題になった糖質制限ではパンや米などのいわゆる炭水化物はタブーとされていました。
しかし炭水化物を全く摂らないのも、エネルギーが不足したりお腹と心が満たされないために間食量が増えるリスクが高まります。
エネルギーが上手く補給できないと代謝も下がり活動効率も下がるため、1日1回でもいいので米を食べるようにしましょう。
米は水分量が多く膨張して満腹感が得やすく、パンやパスタと比較すると油分や添加物が少ないので健康的に食べられます。
肉・魚は淡白な味付けのものをたくさん食べる
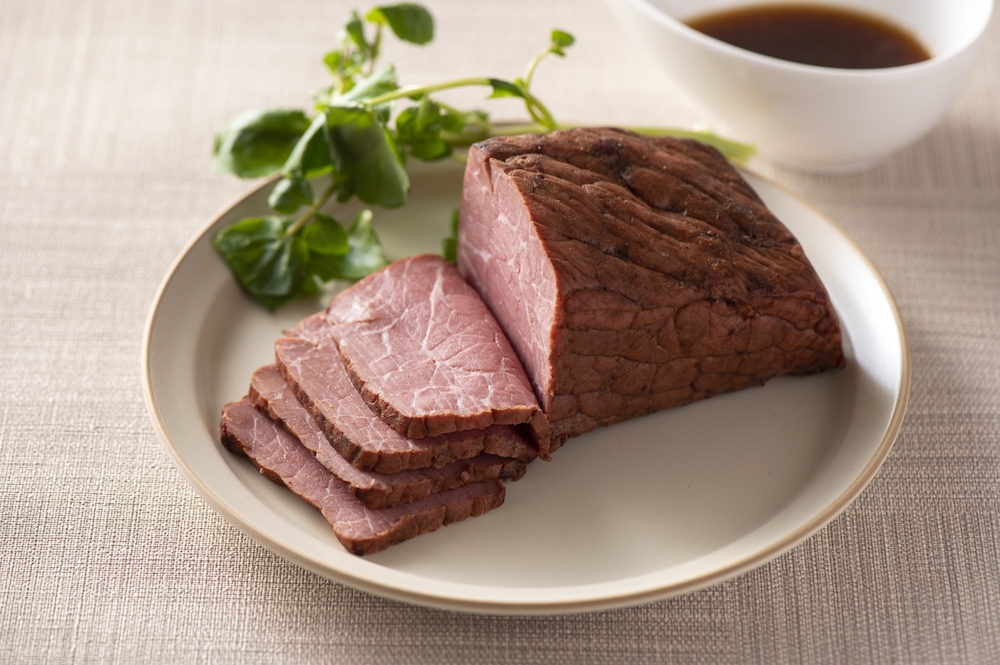
ダイエット中は肉はNGと思われる方も多いですが、それは誤解です。
脂身の少ない肉だったり、蒸し焼きや煮るなど油をあまり使わない調理方法ならば寧ろ肉は積極的に食べた方が健康・美容作りをサポートするタンパク質が補給できるためオススメです。
カロリーを抑えるのであれば鶏肉や魚、卵が良いですが、脂肪燃焼を狙うならL-カルニチンが多く含まれる羊や牛、豚を中心に食べるようにしましょう。
自分の体質にあう食事サイクルを見つける

全く同じ体質の人が存在しないように、体に合う食事サイクルも1人1人異なります。
体質に合わないのに特定の時間だけたくさん食べたり逆に食べなかったりすると、消化のリズムが崩れて体調が悪くなったり思わぬ時間に空腹を覚えストレスを感じたりします。
そうなると食事ダイエットを続けていくことが難しくなりますね。
なので1日の最終的な食事量は維持しつつ、その中でどの時間帯でしっかり食べ逆に控えるのが快適なのかを模索してみましょう。
3食規則正しく食べることだけが正しいわけではなく、人によっては少量の食事を5回くらいに分けて摂ると調子が良かったり、朝食で1日に必要な摂取カロリーの大半を補給してしまえば以降の食事は殆ど必要ないというパターンもあります。
「食事内容は○○でなくてはいけない」などといったダイエット論に縛られず、体質に合った無理のない食事をしていきましょう。