水島亜莉沙〜人気ブロウティスト誕生秘話 Vol.3〜
「造顔美眉」のコンセプトのもと、確立された理論と確かな技術で眉毛をデザインするブロウティスト水島亜莉沙。自身のサロン「Ribby」の運営やスクールでの講師等、その活躍はとどまることを知らない。そんな当代きっての人気ブロウティストの誕生の秘密とは?ブロウティスト水島亜莉沙の過去・現在・未来に迫る。(敬称略)
造顔美眉

眉毛のデザインや描き方を学ぶため、水島はJAPAN BROWTIST SCHOOLに通い始めた。そこで改めて眉毛の理論に衝撃を受けた。
「なぜ眉毛があるのか?から始まり、根本的な理論から勉強し直しました」
水島は現在、「造顔美眉」のコンセプトのもと、自身のサロン「Ribby」にて眉毛デザインの大切さを説いている。
「サロンでは、顔を造る為に眉を造る技術という事で「造顔美眉」というメニュー名にしました。お陰様で、今では造顔美眉でご来店のお客様が100%、リピーターが80%以上で2カ月先まで予約が埋まるようになりました。また、眉の魅力にのめり込み、技術を取得した眉スクールのインストラクターも取得しました。現在はサロン業と講師業を両立してますが、眉の技術も継続して学び続けています」
ブロウティスト

実際に体感している読者の方も多いと思うが、眉毛デザインの流行の兆しは既に現出している。
「眉毛が雑誌で特集されたりして、今ブームになっていますね。ブロウティストを目指す方や、業界に参入するまつげメーカーも増えてきています」
自身のサロン「Ribby」を運営する一方、水島はJAPAN BROWTIST SCHOOLでの講師という肩書きも有している。昨今の眉毛ブームも相まって、生徒の数も年々増加中である。
「うちの学校にも美容師さんの生徒が多いですね。私は眉毛のデザインを学ぶ為に、色々なところに勉強に行きました。最終的になんでこの学校(JAPAN BROWTIST SCHOOL)にたどり着いたかと言うと、根本的な理論が他とは違ったからです」
JAPAN BROWTIST SCHOOLは、水島が最も身に付けたかった眉毛のデザイン理論を教えてくれた。
「技術というのは応用であり、応用ばかり学んでいてもお客様への対応力は身に付きません。もし眉毛のスクールを探しているのでしたら、まずは根本的な理論をきちんと教えてくれるスクールに通うことがオススメです。授業料も安くないので、学校に行って何も身に付かないとなると、時間もお金も無駄になりますから」
未来

「Ribby」をオープンして4年、その間に業界を取り巻く環境も変わってきた。
「マツエク業界は既に飽和状態にあり、価格を下げて人数をこなすか、高い技術を高単価で売るかの2つに分かれています。自分としては、ブロウティストは後者になって欲しいと思っていますし、そのための勉強をスクールでは教えています」
自分の技術に自信があるからこそ、それを安売りすることはない。
「私は理論でデザインする為、感性ではやっていません。ですので、どんな顔や眉毛の人が来ても対応できます。そこは自信がありますね」
今後はブロウティストの育成にさらに力を注いでいくつもりだ。
「自分のサロンも好きですが、ブロウティストを育成する方が自分に向いている気がしています。高い技術を有する素晴らしいブロウティストを輩出していきたいですね。眉毛はとても大切であり、時にその人の人生をも変えてしまいますから」
完
「造顔美眉」のコンセプトのもと、確立された理論と確かな技術で眉毛をデザインするブロウティスト水島亜莉沙。自身のサロン「Ribby」の運営やスクールでの講師等、その活躍はとどまることを知らない。そんな当代きっての人気ブロウティストの誕生の秘密とは?ブロウティスト水島亜莉沙の過去・現在・未来に迫る。(敬称略)
帰国

オーストラリアでの半年間のワーキングホリデーを終え、水島は日本に帰国した。
「帰国してからは、まつ毛エクステとアートメイクのサロンで働きました」
途中、シンガポールでの勤務も経験した。
「4ヶ月間だけでしたが、シンガポール店の手伝いもしました。現地の方の施術もしていましたが、メインは現地のスタッフに技術を教えることでした」
約5年間、まつ毛エクステとアートメイクのサロンで働き、通信課程で美容師免許も取得した。そして、念願だった自分のサロン「Ribby」を東京の代官山にオープンさせた。
「前の会社にいた時は、自分の思うように動けなかったというか・・・。集客やメニューも自分が思うようにやりたかったというのが、独立のきっかけですね」
独立

代官山に出店することは最初から決めていた。
「以前は渋谷で働いていたので、渋谷とは異なる客層の場所を探していたのですが、代官山は年齢層が高くていいなと思っていました。高級志向というか、ワンランク上の美容を求める人のための技術者になりたいと思っていましたので。周りからは、「代官山は集客しにくいよ」と言われましたが(笑)」
最初はまつ毛エクステからスタートした「Ribby」だったが、現在は眉毛にシフトしている。
「サロンオープン当初、独自の技術で考案したのが眉毛エクステでした」
眉毛エクステとはいわゆるまつ毛エクステの眉毛バージョンである
「もちろん眉毛エクステのスクールなども一切なかったので、独学で技術を身に付けました。そもそも使用する毛がなかったので自分で作ったりしました」
これまでになかった眉毛エクステは瞬く間に広がった。
眉毛エクステ

眉毛エクステを開始して分かったことは、眉毛がないから来店するお客様が多いと思いきや、眉毛があるのに来店する人がほとんどであるという事だった。
「どうやって描いていいか分からない、間違ったセルフケアをしている、自分に似合う眉毛が分からない、眉を変える勇気がないなど・・・。眉毛迷子の方がほとんどでした。眉がない人よりも、眉のあらゆるコンプレックスを解消したく、眉毛のエクステをしたいう方が圧倒的に多かったですね」
しかし、水島はある悩みを抱えていた。眉毛エクステはただ毛を増やすだけの施術であるため、お客様の満足度を100%叶える事ができなかったのだ。
「眉に関しては老若男女、年齢問わず悩んでいる事が分かったため、眉毛の需要はヘアサロンぐらいの需要があるのではと思いました。そこで、眉の本当のデザイン効果と、それを綺麗に引き立たせることができるワキシングケアがとても重要で、かつ需要があると考えました」
眉毛の可能性を感じた水島は、もう一度眉毛のデザインや描き方を最初から学び直す必要があると痛感した。
「眉を変えると顔が変わリ、人生が変わってしまうほど、眉はとても重要なものです。なので、安易な技術でお客様の顔を触ってはいけないと思い、一からしっかりとしたデザイン理論、技術を学びました」
続く
「造顔美眉」のコンセプトのもと、確立された理論と確かな技術で眉毛をデザインするブロウティスト水島亜莉沙。自身のサロン「Ribby」の運営やスクールでの講師等、その活躍はとどまることを知らない。そんな当代きっての人気ブロウティストの誕生の秘密とは?ブロウティスト水島亜莉沙の過去・現在・未来に迫る。(敬称略)
美容部員

出身は富山県。小・中学生の時はテニスに熱中し、卒業後は地元の高校に進学した。
「高校時代は部活もやっていなかったので、毎日遊んでいましたね。勉強は好きじゃなかったので、全くしていなかったです(笑)」
高校を卒業後は、地元の富山県で美容部員として働いた。
「中学生ぐらいからコスメやメイクをするのが好きだったので、美容に関わる仕事を探しているときにちょうど美容部員の募集を見つけたという感じです」
美容部員として順調に働いていた水島だったが、その後の人生を変える転機が訪れた。
「仕事の一環で資生堂の撮影があったのですが、その時のヘアメイクさんを見て「かっこいいな」と憧れて、ヘアメイクの勉強をしたいと思うようになりました」
東京

東京からヘアメイクのスペシャリストが来て一緒に仕事をする度に、ヘアメイクの勉強をしたいという気持ちが徐々に大きくなっていった。そして、就職して1年経った時に、満を辞してヘアメイクの勉強をするために東京に行くことに決めた。
「富山を離れて東京の専門学校に入学しました」
ヘアメイクの専門学校を卒業後、美容室で働きながら今度は通信課程での美容師免許取得を目指した。
「髪の毛の勉強もしたかったので、美容師免許を取得するために日本美容専門学校の通信課程に入学しました。池袋の美容室で働きながら勉強していました」
オーストラリア

日本美容専門学校の通信課程に入学した水島は、働きながら美容師免許の取得を目指した。そして、池袋の美容室で働いて1年半ぐらいが経過した頃、水島は突如オーストラリアに旅立った。
「ワーキングホリデーでオーストラリアに行きました。行ける時に行きたいなと思って・・・。」
オーストラリアでは、シェアハウスで生活しながら半年間過ごした
「最初の2週間は現地の学校に行きました。その後は生活するためにお金を稼ぐ必要があったので、ネイルサロンや美容室で働いていましたね」
オーストラリアでの経験は、水島にとって大きな刺激になった。
「ゴールドコーストに住んでいて、たまに旅行でフレーザー島やブリスベンとか行ったぐらいですが、いろいろな国の人と出会えて話を聞けたのはすごく良かったですね」
続く
まだマツエクが現在のように流行する以前にマツエクに魅せられ、その道を極めるべく邁進している女性がここにいる。自身のマツエクサロンを経営しながらアイラッシュシミュレーターを開発し、さらには松風公認エデュケーターも務める伊東真紀が語る、これまでとこれから。(敬称略)
東京

地元では初となるまつげ専門店「アンジェラ」をオープンさせた伊東。マツエクが珍しかったということもあり、お客さんが絶えなかった。
「当時は子供も小さかったので、子育てしながらやっていましたね」
30歳の時に、3度目の転機が訪れた。地元密着型のサロンで3年間営業を続けた伊東は、顧客が徐々に増えていったタイミングで東京進出を決意。新宿でサロン展開することとなり、長野から家族で移住した。今から10年前だった。
「ちょうどその時に東京の方と再婚することになったのですが、私の妹と高校時代に一緒に住んでいた友達を巻き込んで、2人に長野のお店を任せて東京に出てきました。その二人はもう10年以上やってくれています」
東京に出てきた伊東は、新宿や白金のお店を間借りしてマツエクをやっていた。
「すぐには自分のお店を出すことができなかったので、整体のお店の一角を間借りする形でマツエクの施術をしたりしていました」
Angela

しばらく東京にいた伊東だったが、再婚の話がなくなり一旦長野に帰ることになった。
「しばらくは長野にいたのですが、5年前にまた子供二人と東京に出てきました。」
伊東が東京にもう一度来たことには、理由があった。
「10年前に自分が作った技術があったのですが、それを広めたくて東京に再度出てきました。長野では15年やっているので、マツエクといえばここだよねということでお客様が来てくれるのですが、何も知らない場所でこの技術をどう見てもらえるのかを確かめたかったというのがありますね」
もう一度東京に出てきた伊東は、幡ヶ谷にお店を構えた。
「幡ヶ谷は特に縁があったわけではないのですが、どことなく自分の田舎に似ているというか・・・。新宿や白金で間借りしてやっていた時にはなんか違うなと感じていたのですが、ここはコミュニケーションができる街だなと思いました。自分らしく働ける街だと思っています」
大事に育ててきた地元のサロン「アンジェラ」は、信頼できる妹と親友が引き継いでくれた。しかし、大切にしてきた顧客を2人に任せるとなった時に、「いつもと違う」というクレームを顧客から受けた。真摯に顧客と向き合ってくれていた2人だったが、それでも仕上がりの満足度が顧客の理想と合致していなかったのだ。
「どうやってお客様にあったデザインを提案できるか、また、お客様が施術者に対してどのようにして希望のデザインを伝えるのがベストなのかと考えました。私ができることを他の施術者でもうまく再現できるようになって欲しいと思いましたし、お客様とももっと密にコミュニケーションが取れるようになって欲しかったので・・・」
そうして悩んだ末に生まれたのが、「アイラッシュシミュレーター」と呼ばれるものである。これを活用することで、カウンセリングの際の提案がすごく具体的になり、顧客の不満は減っていった。その後、アイラッシュシミュレーターはそのビジュアルのキュートさと機能性で業界でも話題となり、まつエクカウンセリングのスタンダードになるまでに至った。
マツエクの未来

10年前に自身の目のコンプレックスから、個々の悩みに対応できるエクステという新しい切り口で「アイラインエクステ」を考案した。アイラインエクステにはなんと200通り以上のデザインのバリエーションがある。これにより顧客の悩みを解消したり、理想とする目元へ限りなく近付けるパーソナルデザインを作ることが可能となった。
「最初は感性で形を作り、その後理論立てて技術として組み立てていくのはとても大変な作業しでたが、非常にやりがいがありました。何よりも、アイラインエクステを考案してからリピーターも増え、お客様の満足度も確実に上がりました。これは絶対にいい技術だという手応えがあったんです。自分の目にコンプレックスがあったからこそ、目にコンプレックスがあるお客様の気持ちが分かるし、せっかく目元を任せてもらえるのだから、全てのお客様にベストな目元を作ってあげたいと思いました」
考案してから10年以上経つアイラインエクステだが、現在ではアイラインエクステの技術習得の証である「アイラッシュソムリエ」という資格も出来た。アイラインエクステは業界公式の技術になった。
「テクニカルを教えるスクールは沢山ありますが、アイラインエクステは高度な技術を有する人であればその技術を応用して、豊富な知識と多角的な分析及びカウンセリング方法を学ぶ事で誰でも導入できるという点が特徴です。この技術を考えサロンに導入した10年前は、感覚的人間の私には施術をすることは出来ても、理論を説明する事が出来ませんでした」
当初からアイラインエクステは絶対的な自信のある素晴らしい技術であると確信していたが、質問されてもそれを理論的に明確に答えられない自分が悔しかった。しかし、ある出会いが状況を一変させた。
「3年前にメイクの先生(原本氏)に出会い、メイクの理論技術を学びました。その時に初めてアイラインエクステを理論化しようと考え、そこから3年かけてアイラインエクステの教科書となる資料を作りました。トータルで500ページ以上になりました」
伊東の挑戦はまだ終わらない。
「アイラインエクステをスタンダードな技術にするのが私の夢です。施術できる技術者が増えていくことで、エクステの業界が少しずつ変わって行ったらいいと思っています。また、本数での価格設定や毛質で価格を変えるなどの技術者目線のメニューではなく、お客様に寄り添うお客様目線のメニューになることでより喜んでくれるお客様が増えて、結果的にエクステ業界がもっと盛り上がれば本望ですね」
完

まだマツエクが現在のように流行する以前にマツエクに魅せられ、その道を極めるべく邁進している女性がここにいる。自身のマツエクサロンを経営しながらアイラッシュシミュレーターを開発し、さらには松風公認エデュケーターも務める伊東真紀が語る、これまでとこれから。(敬称略)
ポーラ化粧品

高校卒業後に初めて入った会社で、先輩からのいじめを受けて3ヶ月で退社した伊東だったが、そこでかけられた言葉が自分の人生を大きく動かす原動力になった。
「その時の職場の先輩に、「自分の人生は誰も保証してくれないのだから、自分が好きなことをやった方がいいよ」とアドバイスをもらいました。その言葉は今でも印象に残っています。それがきっかけになり、美容の世界がいいなと思い地元に戻りポーラ化粧品に入社しました」
先輩の金言が美容業界で働いていこうという原動力となり、ポーラ化粧品では本来の自分を取り戻すことができた。
「あそこは全て歩合制だったのですが、すごく楽しかったですね。時間も自由だし、縛られることなく自分の好きなように働けました」
新たな船出

大好きな美容の仕事で力を発揮していた伊東だったが、20歳の時に社内独立という形で自分の店を持った。
「私の売り上げが良かったので、ポーラ化粧品の中で独立して私だけの店鋪を持たせてもらいました。当時は3〜4人雇っていました」
しかし、念願の自分の店を持てて楽しく仕事ができるようになるはずが、逆に窮屈さを感じるようになった。
「お店の従業員の面倒を見たりするのが大変というか、苦手でした。当時は自分も20歳で人間ができていなかったので・・・。自由にできなくなることにフラストレーションを感じていました」
結果的に1年でその店は辞めた。そして、23歳で結婚をし妊娠したことで最初の転機が訪れた。
「当時フランチャイズ型の店舗で半分自営業の形で働いていたのですが、スタッフの管理をしながらの子育ては難しいと感じ、改めて独立して地元・長野でエステサロンを開業しました」
子育てをしながらサロンワークを続け、その間に第2子にも恵まれた。
まつ毛エクステとの出会い

27歳の時に、2回目の転機が訪れた。離婚をきっかけに再度自分の将来について考えざるを得なくなった。これからの選択は自分だけでなく子供たちの将来も左右する。エステだけでは心許ないと感じていた時に出会ったのが、まつげエクステだった。
「地元ではまつげエクステのお店は1店舗もなかったし、まつげエクステって何?って感じでしたね。何かいい仕事がないかと調べていた時に偶然見つけて、これだ!と思ったんです。自分の目は一重で、目の形に昔からすごくコンプレックスがあって。まつげエクステで自分のコンプレックスがカバーできるのではないか、かわいくなれるのならやってみたいと思いました」
最初の入口は自分のコンプレックス解消の手段だったが、それがまつげエクステとの長い付き合いのきっかけとなる。当時はまだまつげエクステ自体がメジャーではない時代。母親の支援を得て、まつげエクステの民間資格も取得した。
「親に20万円借りてまつ毛エクステの民間の資格を取りに行きました。5時間の講習で20万円という、今では考えられない値段でした(笑)。習った翌日から既存のお客さんに施術して、翌月には母に借りたお金を返金しました」
技術を習得した伊東は、地元では初となるまつげ専門店「アンジェラ」をオープン。今までのエステの顧客と口コミだけで地道にサロンを大きくした。離婚時に仕事も子育ても絶対に妥協しないと決めた伊東だったが、当時はまだシングルマザーに対しての理解も薄く、女性は専業主婦が幸せだと言われていた時代。子育てしながら仕事をする事で非常に肩身の狭い思いをしたことも多々あった。
「今思うとなかなかハードな毎日でしたが、とにかくなんとか軌道に乗せたいと夢中でした。部活で培った体育会系の根性や負けず嫌いの性格のおかげなのか、絶対に挫折したくなかったんです。何よりもかわいい子供たちは私がいないと生きていけません。それが頑張る原動力でした。だからこそここまで乗り切れたのだと思います」
子供が風邪をひいても子供を見ながら仕事ができるように自宅サロンからスタートし、子供が寝てからのわずかな隙間時間でハーブやアロマの資格取得のための猛勉強を開始した。まつエク以外にもハンドメイド化粧品のフランチャイズやブライダルメイク、ファイシャルエステ等、サロンを続ける上で役に立ちそうなものは全て習得していった。そして、30歳の時に3度目の転機が訪れた。
続く
まだマツエクが現在のように流行する以前にマツエクに魅せられ、その道を極めるべく邁進している女性がここにいる。自身のマツエクサロンを経営しながらアイラッシュシミュレーターを開発し、さらには松風公認エデュケーターも務める伊東真紀が語る、これまでとこれから。(敬称略)
活発だった子供時代

伊東は長野県下伊那郡阿南町出身で4人兄弟の2番目。保育園時代から気が強かった。
「保育園の時は友達に喧嘩をふっかけたりとかしていました(笑)。小学校の時は剣道や習字、そろばんを習ったりしていましたね」
小学校を卒業した伊東は、地元の小さな中学校に入学した。
「保育園から中学校まで13人の同じクラスで、女子は7人しかいませんでした。部活もバレー部しかありませんでした。山奥の盆地にあった中学校なので、毎日バレーの練習をしていましたね」
高校時代は親元を離れて寮で生活していた。
「田舎すぎて地元に高校がなかったので、自宅から車で1時間位の離れた場所にある飯田市の高校に通いました。自宅から遠くて通えないので、学生寮のようなところに友達数人と住んでいました」
イルカの調教師

最初は数人で共同生活をしていたが、そこで提供される食事が美味しくなかったので、途中から一人部屋に移って自炊を始めた。
「もともと自由が好きなので、ホームシックにはかからなかったですね。特に気にはならなかったです」
中学校でやっていたバレーはやめて、高校からは空手を始めた。
「小学校の時に剣道もしていたので、武道系が好きなのかもしれないですね」
やがて高校2年生になり、進路を決める時期に差し掛かった。当時の伊東にはどうしてもなりたい職業があった。
「高校の時は特に美容にも興味がなくて、イルカが好きだったのでイルカの調教師になるのが夢でした」
イルカの調教師になるために、名古屋にあるイルカの施設に見学に行った。
「イルカがいる施設が名古屋にあったので、見学に行ってみました。しかし、イルカを見た瞬間に「やめよう」と思いました。触るのが嫌だなと思って(笑)。イルカの調教師は自分には向いていないと思い諦めました」
社会人1年目

高校はなんとかギリギリで卒業した。
「通っていた高校が進学校だったため、何も勉強してなかった自分はかなりヤバイ感じでした。なんとか卒業した感じです」
高校を卒業した伊東は、名古屋で一人暮らしを始めた。
「動物に関わる仕事がいいと思って、犬の調教師になろうと思いました。私は4人兄弟なので、最初に学費を作ってから専門学校に行こうと考えていたのですが、給料が良かったので母から勧められた名古屋にある痩身エステで働き始めました」
生まれ育った長野県を出て、名古屋で社会人としての一人暮らしが始まった。
「その会社は、すごくつらくて入社して3ヶ月で辞めました。朝から夜まで寝る時間もなく働きましたし、夜中に研修があったりして、逆に自分がどんどん痩せていきました(笑)」
仕事の過酷さだけでなく、中間管理職の上司による陰湿ないじめもあった。
「私が店長やマネージャーに可愛がってもらっていたので、それが気に入らなくてその間のポジションの上司にすごくいじめられましたね。入社して3ヶ月で辞めるのは応援してくれていた両親に申し訳ないと思いつつ、事情を話すと両親も「それなら辞めて好きなことやれば?」と言ってくれたので、最終的には辞めました」
入社して3ヶ月で退社した伊東は、失意のなか地元に戻ることになった。
続く
主戦場を原宿から中目黒へと移し、今なお美容業界をリードし続ける「サトーマリ」(siika NIKAI)。 私たちはその華やかな活動に目が行きがちだが、同時にスタッフ及び美容業界の環境改善のために日々戦っている。独立・出産・子育てを経てたどり着いた現在の境地とは?美容師サトーマリのこれまでとこれから。(敬称略)
世代間闘争
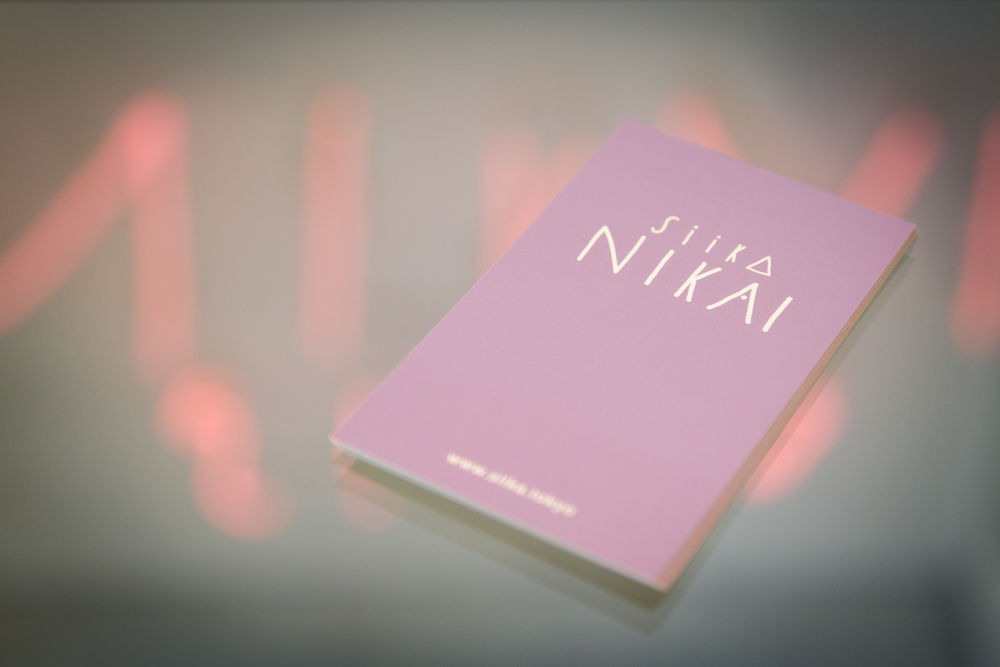
サトーが美容業界に入った当時と今とでは、業界を取り巻く状況も変わってきている。
「私はカリスマ美容師ブームで一気に美容師が膨れ上がったときの世代です。周りはみんなアラフォーになりましたが、全員が独立できるわけでもなく・・・。これからさらに美容師人口が減っていく中、今の若い子はチャンスなのでどんどんやった方がいいとは思いますね。競争相手がどんどんいなくなると思うので」
若い美容師にとってチャンスなのが今の美容業界であり、サトー自身もチャンスを掴んできたから今がある。
「自分たちの世代が業界を一番ごちゃ混ぜにしているとは思いますね。この世代は敵が多いのでハングリー精神が必要ですが、今の若い世代は逆に敵が少ないのでハングリー精神が必要ありません。そこに対して、もっとやらなければダメだろうという自分たち世代と、福利厚生や休みが欲しいという若い世代が戦っているなというイメージですね」
出産・育児と美容師の両立

美容業界全体としてみると、育児と美容師を両立させるための環境が整っているとは決して言い難い。
「今子供を生んで育てている世代の美容師は、いわゆる代わりがいる世代なので、特に男性オーナーなどからは重宝されない部分があるかもしれません。しかし、これからはそうも言っていられないと思います。自分たちの10〜20歳下の世代などは、これからママさん美容師のために託児所を作るのが当たり前になると思いますね」
若い美容師人口が減っている昨今、労働環境の整備は急務である。
「そのうちママさん美容師専門の美容室ができると思いますし、給料形態もどんどん変わってくるだろうなとは思います」
サトー自身も、若いスタッフが将来出産しても美容師をずっと続けられるための環境作りをしている最中である。
「とりあえず、何かそういう仕組みを作るにしても資金が必要で、自分たちに力がないとそこには行けません。なので、まずは自分たちの組織を大きくして安定させることを考えています。今はその子たちが育ったときに、自分達がいかようにも動いて対処してあげられるような環境、ベース作りをしているところですね」
未来

自分もかつては育ててもらったように、今は自分が育てる側だ。若い美容師や美容学生に期待する部分は大きい。
「美容師はずっと高みを望めるので、将来的に見ても楽しい職業だと思います。歳を取っても流行を追わなければならないので、若い感覚を常にどこかで持っている必要がありますが、意識的にそのような感覚が必要な職業はあまりないですしね。そこが良くて美容師を目指している学生は多いと思いますが、そういう意味では決して裏切らない職業だと思います」
仕事で大切にしているのは「人との繋がり」である。
「美容師とは人との繋がりだと思います。いくら技術があっても人とうまくできない子はやめてしまいますし。お客さん、他の美容師、編集さんや取引先の方等、ちゃんと人に興味がなければ成功しないと思いますね」
思い描く未来に向けて、今は着実に進んでいる。
「将来的にはゆっくりしたいですね。結局ゆっくりできないとは思いますけど(笑)。サロンワークはずっとしていきたいとは思っていますが、今は人を育てるというのが一番です。多店舗展開したいとかは特にないのですが、あと1〜2店舗は出さなくてはいけないのかなとは思います。スタッフの面倒をずっと見てあげたいので」
育児と仕事の両立等、美容業界が抱える問題は数多い。それらを解決するまでサトーマリの戦いは終わらない。ゆっくりするのはもう少し後になりそうだ。
完
主戦場を原宿から中目黒へと移し、今なお美容業界をリードし続ける「サトーマリ」(siika NIKAI)。 私たちはその華やかな活動に目が行きがちだが、同時にスタッフ及び美容業界の環境改善のために日々戦っている。独立・出産・子育てを経てたどり着いた現在の境地とは?美容師サトーマリのこれまでとこれから。(敬称略)
社会の洗礼

ハリウッド美容専門学校を卒後したサトーは、原宿の美容室に入社した。
「今考えてみても、1年目が一番辛かったですね。褒められなかったですし、いわゆる「理不尽さ」というのは社会に出ないと経験しないですから・・・。小さな店で同期がいなかったので、味方もいませんでした」
誰もが一度は経験する社会人としての洗礼を浴びた。
「モデルハントが辛いとか、休みがないのが嫌だとかはあまり思わなかったですね。私だけ怒られるとか、全部私のせいになるということの方が嫌でした。練習のために朝早く起きるとかは、何とも思いませんでした」
転機

そして、空前の読者モデルブームが到来。時代の波にも乗り、「サトーマリ」の名前は瞬く間に広まった。
「当時は雑誌が全盛期で、私はメンズから入ったのでCHOKI CHOKIで色々やらせてもらいました。読モブームの真っ只中だったので、読モがよくサロンに遊びに来ていました。そのうちAMIAYAちゃんが出てきて、髪の毛を担当するようになってから女性誌の依頼が来るようになりました。その結果、一般誌にたくさん出ているということで業界誌にも載るようになりましたね」
今やサトーマリの代名詞とも言えるカラーのイメージが定着したのもこの頃だった。
「毛先カラーとかも最初はAMIAYAちゃんの希望でやったのですが、当時は他にやっている人がいなくてそこから流行りました。運が良かったですね。それでカラーのイメージも付きました」
時代の波にも乗り、一躍有名美容師の仲間入りを果たしたサトーだったが、妊娠・出産を境に人生の転機が訪れた。
「妊娠した時に、そのサロンでは子供を育てながら働くという環境がまだ整っていませんでした。そういった不安から独立を決めました」
自分が求める環境がないのなら、自分でその環境を作るしかないという思いがサトーを突き動かした。
独立

2016年2月、学芸大学駅から徒歩2分の場所に「siika」(シーカ)を、2019年には中目黒に「siika NIKAI」(シーカ ニカイ)をオープンした。
「原宿はどちらかというと、「記念に1回だけ原宿で切ろう」という若いお客さんが多く、新規客で回す場合がほとんどです。もしお客さんがついても30歳を過ぎると足が遠のくことが多いので、原宿でずっとやっていくにはサロンワークだけではなく、情報発信等あらゆることをやらなくてはいけません。当時の自分は、それに疲れた時でした」
学芸大学は、そんな当時のサトーの心境と理想に合致した街だった。
「それまで地域密着のお店をやったことがなかったので、やってみたかったというのがあります。その方が意外と美容師としても楽しいのではないかと思って」
しかし、当初の思惑とは異なり想像以上に自分のスタイルがはまらなかった。
「自分が可愛くないと思うスタイルが受け入れられるのを見たときに、自分がハマってないと思いました。それならもう少し渋谷に寄ろうと思い、学芸大学のお客さんもいたので、近いところはどこだろうとなったときに思い付いたのが中目黒でした」
独立する前と後では、当初描いていたイメージにそこまで相違は無い。
「美容学校を卒業して就職する時もそうだったのですが、意外と期待していないというか、最悪を想定して物事を始めるので(笑)。ただ、人が増えれば増えるほど、それぞれ色々な思いが出てくるので、その全てに歩み寄ることの厳しさは感じています」
続く
主戦場を原宿から中目黒へと移し、今なお美容業界をリードし続ける「サトーマリ」(siika NIKAI)。 私たちはその華やかな活動に目が行きがちだが、同時にスタッフ及び美容業界の環境改善のために日々戦っている。独立・出産・子育てを経てたどり着いた現在の境地とは?美容師サトーマリのこれまでとこれから。(敬称略)
厳格な両親

生まれは茨城県。両親はともに教師だったこともあり、身なりなどにとても厳しい家庭環境に育った。
「小学生の頃は習い事をたくさんしていましたね。そろばん、ピアノ、英語などを習っていました」
地元の中学校に入学したサトーは、バドミントン部に入部した。
「両親がともに体育教師でバドミントンをやっていたので、それなら私も練習しなくて上手くできるかもと思ってバドミントン部に入部しました。運動神経は悪くもないのですが、良くもないという感じでした(笑)」
中学から高校にかけては、少しだけ反抗期だった。
「両親の教育が厳しかった分、ちょっとやだなという思いがありましたね。髪の毛も友達は好きにやっているのに、自分は思い通りにできないのがすごいストレスで・・・。「高校を卒業したら好きにしていい」と両親に子供の頃から言われていたので、それまで我慢していた感じですね」
進路

中学校を卒業したサトーは、親に勧められた高校に入学した。
「勉強はほとんどやらなかったですね。部活もやっていなかったので、毎日暇だなと思っていました(笑)。バイトもしましたが、それもそんなに続かなかったですし」
やがて高校2年生になり、進路を決めなければならない時期に差し掛かった。
「当時は就職氷河期でしたし、大学に行っても意味がないような気がして・・・。だったら手に職を付けたいなと考えていました」
数ある専門職の中で選んだのは、現在の美容師という職業だった。
「両親が厳しかったので昔から髪の毛とかあまり自由にできなかったのですが、一般企業に入ってまた髪型をうるさく言われるのも嫌だったので、それだったら美容師になろうと思いました。母親は大学に行かせたかったようですが・・・」
東京

当時は空前のカリスマ美容師ブーム。美容専門学校に入学するだけでも一苦労だった。8校受験して、合格したのはハリウッド美容専門学校だけだった。
「美容専門学校時代は楽しかったですね。ホームシックなども特になりませんでしたし。専門学校に通いながら、メキシコ料理屋さんでアルバイトもしていました」
美容専門学生時代、特に大変だったり辛かったりという思い出はない。
「私は器用でもないのですが不器用でもないので、美容専門学校の勉強などで苦労することは特になかったですね。辛いとかもなかったです」
ハリウッド美容専門学校を卒後したサトーは、原宿の美容室に入社した。
「当時は雑誌に載っていればどこでも良かったですし、実際にサロンに行ってみると人も良さそうだったので決めました」
いよいよ社会人としての、そして美容師としての新しい生活が始まった。
続く